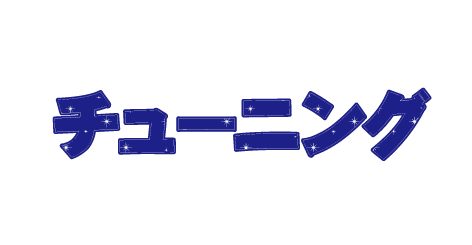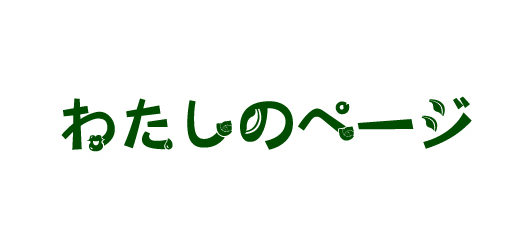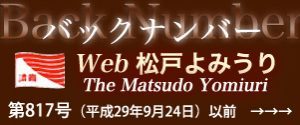本よみ松よみ堂
町田そのこ著『わたしの知る花』
時代とともに変わるものと、長い時を超えても変わらない人生の大切なこと
物語は15歳の高校一年生、安珠(あんじゅ)が葛城平(かつらぎへい)という老人と出会うところから始まる。平はいつも手製の画板を持ち歩き、スケッチブックに絵を描いている。それには絵だけではなく文章が添えられている。
安珠には、奏斗(かなと)という幼馴染がいる。性別をこえて「親友」と呼べる存在。思春期の二人は、お互いの関係をうまく把握しきれずにいる。安珠は奏斗と仲たがいをしてしまった。安珠は奏斗が子どもの頃から抱いている悩みを知りながら、寄り添えていなかった自分に気づく。
平は「タイミングってのが、ある」と話す。「心を分かち合える人生の伴侶になるタイミングも、あるだろうな。ひとってのは、どれだけ相手を求め合っていても、考え合っていても、タイミングひとつでズレてしまう生き物なんだよ。そして、あんたとその子はいま、そういう大事なタイミングのひとつにいるんだと思う」。
平の言葉には、自身の苦い経験がにじんでいる。77歳の老人と15歳の少女。世代は違えど、人生の大切な部分は変わらないのかもしれない。
とはいえ、外形的には時代は大きく変わった。この物語には、昔の価値観を変えられずに生きていて、孫に嫌われている老人も出てくる。
私の両親の世代の話である。昭和10年代に生まれた母は5人兄弟姉妹だった。母は長女で弟2人と妹2人がいた。弟2人は高校まで行ったが、次女は中学までしか行かせてもらえなかった。成績の良し悪しは関係ない。女だからだ。母は中学生の時に親類の養女になった。高校に行かせてくれると言われたからだ。
私が高校生の頃でも、こうした古い考えはまだ残っていた。「女に学は必要ない」と平気で言う大人がまだいた。
安珠の祖母の悦子も成績が良かったのに、高校に行かせてもらえなかった。苦労して理容師になり、自分の店を持った。その悦子と平が知り合いだったことを安珠は知る。平は何十年もこの町を離れていて、最近戻ってきたのだ。
安珠が仲直りしようとしている奏斗と平は似たところがある。二人とも、男たちからは弱々しいと見られ、時に嘲(あざけ)りを受けるが、女性からは違和感なく受け入れられる。「男らしい」「女らしい」という言葉が人の生き方を縛っていた、と今なら分かる。
平の人生に興味を持った安珠は平のことを調べ始める。平は何を熱心に描いていたのか。祖母・悦子との関係は? 長い長い時を超えて、安珠はある答えにたどり着く。【奥森 広治】
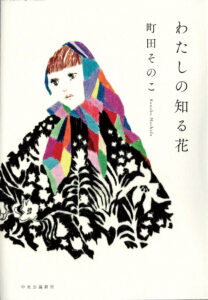
中央公論新社 1700円(税別)