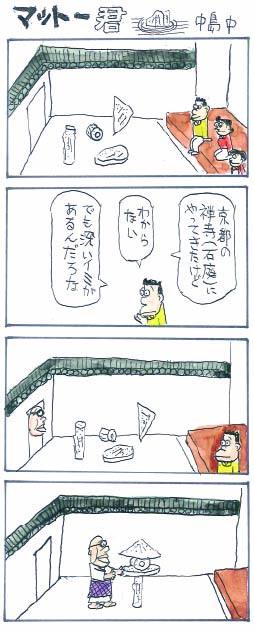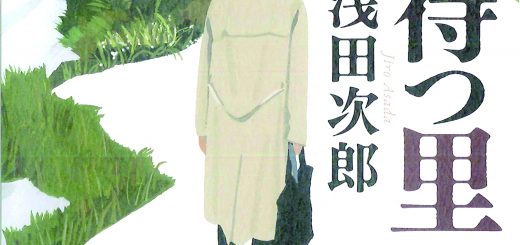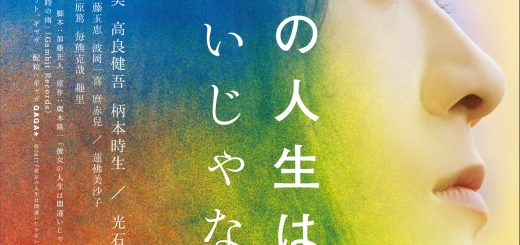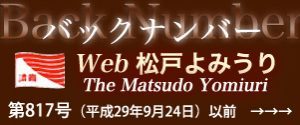わたしのページ(読者投稿)
2025年4月27日

蔭山文江さんの作品
傘寿のお祝いに誕生日の日新聞
先日、遠方に住む父が傘寿の祝いを迎えた。お祝いにかけつけることはできなかったので、いつものプレゼントにプラスで何か変わった物を、と思い歴史好きの父に今年は初めて読売新聞の誕生日の日の新聞(記念日の新聞)を贈ってみることにした。
申し込みの段階でふと心配になった。
今年は終戦から80年の節目を迎えるが、父の誕生日は東京大空襲があった日のちょうど翌日。多数の犠牲者が出て首都が焼け野原になった日の翌日である。そんな日に新聞の発行などできたのかしら、と思ったのだが、なんと読売報知は発行されていた。どうやって発行できたのかとびっくりした。
終戦の歴史がそのまま父の人生だったと思うと、戦争は遠い昔の話ではなく急に現実に迫ってくる。
また母親になった今、未曽有の戦禍の中で離れた地にいたとはいえ、祖母はどんな想いで父を出産したのだろうかと感慨深かった。
当日、お礼のLINEとともに気になる紙面も送られてきた。
「皇軍行動開始」「B29百三十機帝都来襲」、勇ましい文字ばかり並び、言論統制下で事実は伝えられていないがその時代の空気感は生々しく感じることができた。
父はこの珍しいプレゼントを何度も読み込んでくれたらしく、とても喜んでくれた。
その日は東日本大震災の鎮魂の日でもあるので、毎年重みのある一日ではあるのだが、同居する家族たちにお祝いしてもらい穏やかな笑顔の父の写真を見て、いつまでも元気で楽しく過ごして欲しいと心から思った。
(夜空のスピカ)
今年も優しい春の風が吹く
春と呼ばれる時季。夢を与えてくれる春、佐保姫、早春、弥生、啓蟄、催花雨、春霞、春告鳥、花笑う、桜前線。春の言葉の美しさに驚く。
素敵なこの季節に咲き誇る花。花に、祝盃をあげる。
今年もやさしく春の風が吹き、悲しみを癒してくれる。心の内面が軽くなり、季節はきちんと順番にめぐりくる。
薄緑の若葉を透かして吹き抜けるさわやかな風に、もうすぐ夏だネ、と、つぶやき。
明日髪を短くカットしてこよう。(こいぬ)
色とりどりの花を描くように…
リハ施設には将棋や麻雀クラブがありましたが、私には全く縁がないもので困ってしまいました。
他はフラワーアレンジメントクラブがありましたが、これもまた縁がなく、右往左往している間に、しかたなしにそのクラブへ入会することにしました。
初めて座った席の隣は男性が一人、後は女性が十数名並んでいました。もうそれだけでドキドキしました。
やがてテーブル上に新聞紙が配られ、その上に十数本の満開の花々が並べられました。
先生は「まず、どの花を真ん中に生けるかを決め、それから周りを花々で飾って下さいね」と言われました。
私は「エイッ」とばかりに黄色い花を取り中央に刺してみました。
後は無我夢中、色とりどりの花々を絵を描くように生けてみました。短い時間でしたが緊張の中に楽しさも見つけました。今回で13回を迎えましたが、その楽しさは持続しています。
月1回ですが、終わった直後から次の回が待ち遠しくてなりません。あんなにドキドキしたのに。(花は一番)
散歩する身となって分かった事
若い頃は、高齢者の方々は、毎日同じ道を散歩していて、飽きないのか。ただ健康のため、楽しくもない道を歩いているのかと、漠然と思っていた。
いざ自分がその年齢となり、散歩する身となってみると、意外な発見があり、その思いは見事に吹っ切れた。
思い返せば、町の風景など見ていなかった。仕事場へ向かって歩いていただけなのである。
自分の住む町をよく見ていなかった。
家々の色や形、庭の木や花々、空の色、雲のさまざまな模様、風の香り、家々もリフォームしたり、時を経て変わる。そして、季節の移ろいとともに、梅やさくら、花水木、紅葉、水仙、チューリップ、紫陽花、椿、さくら草、菊の花、サルビアなど。蝶も舞い踊り、散歩道は私を楽しませてくれる。鳥のさえずりも快く、平和な町に心から感謝の気持ちが沸く。
そうか、高齢者の方々は、これを楽しみながら日々歩いていたのか。
私は、さくら草の咲く頃、こころワクワクする。たくさんの鉢植えが小さな庭に並べられる。さくら草の花言葉は、「少年時代の希望」「初恋」「憧れ」だそうだ。
遠い昔の初恋の頃を思い浮かべながら、楽しく「さくら草の散歩道」を私は歩いている。(稔台・雑草愚人)
自動車は止まってくれない
衣料量販店の駐車場から出てくる車に、若い男性がぶつかる瞬間を見た。
男性は私の少し前を歩いていて、ぶつかったと言っても、車のスピードはゆっくりで、少し当たった程度でケガなどは無いように見えた。ぶつかった男性は、手で車体を一度だけ叩いて、そのまま行ってしまった。
ぶつかった男性も後ろを歩いていたわたしも、車は止まるものだと思っていたのに止まらなかった。
それから数日後、信号のない道路を渡っている時に危うく車にぶつかりそうになった。止まってくれるだろうと思って渡ったが、ギリギリまで止まってくれず、危なかった。
その時、ある言葉が頭をよぎった。
「車は止まってくれないんです!」。
これは、松戸市と警察署及び防犯協会が協力してやっている「防犯ゼロの日」キャンペーンで、警察の方が話していた言葉だ。
交通事故が多いとされる信号のない交差点などで、車が止まってくれるだろうと思って渡ったら、車は止まってくれずに事故に遭うという話だった。
周囲の状況を楽観的に予測する「だろう」ではダメなのだ。「止まってくれるだろう」ではなく、「止まらないかもしれない」と危険を予測して行動し、
事故を未然に防ぐようにしよう。
これからは、横断歩道であっても、車が止まるのを確認してから渡ろうと心に決めた。(マシュー)
母との確執、手に入れた大切なもの
ここしばらく体調が悪い。かかりつけの病院へ行ったが、医師はどこも悪くないという。いつもと様子が違ったのか、心配してくれた看護師さんにも最近あったことをいろいろと話した。
百歳近かった母が亡くなったこと、そのあとの相続の大変なこと、そして母との生前の関係。
私には姉妹がいるが、私は母にかわいがられた覚えがない。それは周囲から見ても明らかだったらしく、母自身も他の子はかわいかったが私はかわいいと思えなかった、産みたくない子どもは産まなかったのにと言っていた。そこには父と母、祖母と母などさまざまな大人の事情があったらしい。
そんな母が直筆の遺言書を残した。私には何も相続させないと、しっかりした文字が、確かな意志が感じられた。
すると、この話を聞いてくれていた看護師さんが泣き出してしまった。まるで自分自身のことを聞いているようだ、まるで将来の自分の話を聞いているようだと。
私には子どもがいる。みんな同じようにかわいい、みんな愛していると伝えながら育ててきたつもりだ。
母との話はこれまで何度もしてきたし、今回、私がショックを受けていることも知っている。
病院でのことを子どもに話すと「えっ看護師さん泣かせちゃったのー」と軽い返事がまずは返ってきた。ああ良かった、これでいい。看護師さんには悪いが、こんな話に泣けるほど共感、実感できるなんて辛すぎる。
医師からのアドバイスも一言。「精神的なことは体にも影響するよ。治す薬はないよ。お笑い番組でも見て楽しく過ごしなさい」。
欲しくて欲しくて手に入れられなかったものがある。そして確かに手に入れたものが今ここにある。(匿名希望)
新年度から「いいことノート」
毎日がなんとなく同じことの繰り返しかなあと感じていた。
そんな時、「類は友を呼ぶ」とは、いいことはいいことを呼び寄せるともいう、と聞いた。さらに、日々いいことを貯金していくとそれにはいいことの利息がつく、と言っていた。
何のことかというと、毎日(寝る前が一番良いそうだ)その日のいいことを3つ以上箇条書きする「いいことノート」のことである。
いいことをしてもらった、いいことを聞いた、いいことを見た、いいことをした、など。それを日々積み重ねてご機嫌でいるといいことが起こりやすくなる、という仕組みだ。ノート好きの私としてはやらない手はない、と思った。
韓国の軍隊でも毎晩その日の良かったことを3つ書くよう指導されるそうだ。厳しい訓練を耐え抜くメンタルを安らかにさせる効果もあるのだろう。
満開の桜で始まった新年度、1つ目のいいこととして「いいことノート」を始めようと思った。お気に入りのノートを用意し、いいことのタネをメモする携帯用のメモ帳も必要だ。手書きでいいことを味わいたいと思う。これだけでも春めいた気分になる。
いいことを見つけるのは、日常の1つ1つをズームで見ていく感覚で、メリハリのある毎日になりそうだ。
新しいメモ帳を携えて、いいこと集めに一歩を踏み出したところだ。(小金きよしヶ丘・シゲ美 53)
週末にやる子どもとのサッカー
私の楽しみの一つは、週末にやる子どもとのサッカーである。
うちの子はサッカー部に所属し、毎日学校で汗を流している。そんな息子と日曜日になると近所の公園に行き、パスや1対1のボールの取り合いをする。
今年51を迎える私の体力はすぐに限界を感じてしまうが、思い切り走ってボールを追うことは実に爽快だ。それと同時に、1対1で子どもからボールを奪えなかった時は実に悔しい。小学生の時はあれだけ手玉に取っていたのに…。
何はともあれ、「息子よ、一緒に遊んでくれてありがとう。これからもよろしく」。(小金原 S・T 50)
出征した叔父の足跡辿る旅
1921年(大正10年)10月生まれの叔父は、長兄(私の父)の末弟だ。
先の世界大戦出征時の軍服姿も凛々しいセピア色の写真がある。真っすぐ見据える視線の先を想うと戦慄が走る。
一念発起して叔父の本籍地(私の出生地)新潟県に軍歴証明書の発行を依頼した。
すると、陸軍兵籍簿なる履歴の詳細と、第一軍野戦貨物廠略歴が年月日ごとの時系列で羅列されて郵送されてきた。
その資料で初めて、叔父が1944年(昭和19年)5月にマリアナ諸島サイパン島上陸後、歩兵第135連隊に編入され、2か月後の同年7月に玉砕の事実を知った。
私の出生1年前、享年23歳の生涯だった。
2022年5月、「K叔父さんの足跡をたどる心の旅の終焉」と題した、親族に宛てた私の手紙がある。
「私はK叔父さんの遺骨を収集して、祖父の建立した代々墓に納骨するのが夢だった。しかし、はかなくその夢は消えた。K叔父さんの霊が冥界で両親や兄たちと再会出来ることを願って終焉とする。 A子」。
ここで私の活動は終わったはずだった。が、事態は思ってもみなかった方向へと舵を切った。
2022年10月、「遺骨収集団がサイパン島などで順次活動再開」の記事に接する。
サイパンを含めたマリアナ諸島全体の収容検体数966。2023年5月現在、厚労省は戦没者遺骨の身元を特定するDNA鑑定体制を強化するという。サイパン島の埋葬地で遺骨を鑑定する明海大のS教授の写真が掲載されていた。
収容した遺骨と国内の遺族から募った検体を照合調査し鑑定する。親族関係図によると、戦没者(叔父)の続き柄で姪にあたる私はやや希薄のようだ。検体の採取はごく簡単な方法で、2024年2月に提出した。待つこと1年、今年2月に再度、検体提出の依頼を受けた。
再提出の理由は不明だ。
このマッチング作業は膨大で、多分、千にひとつの確率と想像されるが、一縷の望みにかけようと思った。叔父の喜ぶ姿を目の当たりにすると、感動がこみあげてくる。(仲井町 A・T 79)