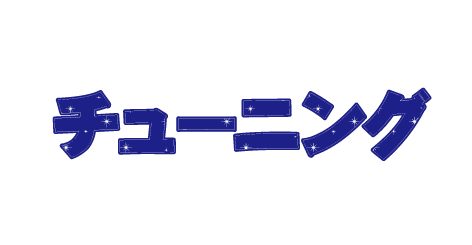松戸の文学散歩
小林一茶・後
江戸末期の俳人・小林一茶(1763年〈宝暦13年〉~1827年〈文政10年〉)を描いた4編の小説・戯曲のうち、前編では藤沢周平の『一茶』と田辺聖子の『ひねくれ一茶』を紹介した。後編では井上ひさしの『小林一茶』と矢代静一の『小林一茶』を紹介する。
一茶の生涯については、前編で藤沢周平の『一茶』をもとに概略をまとめたので、ご参照いただきたい(弊社ホームページに掲載)。 一茶を描けば必ず馬橋が登場する。馬橋には一茶を庇護した油屋・大川立砂(りゅうさ)、斗囿(とゆう)の親子がいた。奥信濃・柏原で生まれた一茶は15歳で江戸に奉公に出る。しかし、奉公先に馴染めずに何度も居場所を変えた。一茶にとって、馬橋は初めて安住できる場所だった。俳諧師としての道を志した一茶は、その後も度々馬橋を訪れることになる。
流山には有力な庇護者で味醂醸造創設者の一人と言われる秋元双樹がおり、馬橋を訪れた一茶は流山にも度々足を運んだ。【戸田 照朗】
井上ひさし『小林一茶』
劇作家で小説家の井上ひさしは昭和9年(1934)山形県川西町生まれ。昭和47年(1972)『手鎖心中』で直木賞。昭和61年(1986)『腹鼓記』『不忠臣蔵』で第20回吉川英治文学賞。『小林一茶』は昭和54年(1979)紀伊国屋演劇賞、翌年読売文学賞を受賞した。平成22年(2010)、75歳で亡くなった。
成美の隠宅での盗難事件を軸に、一茶のこれまでの人生の数々の場面が劇中劇という形で演じられる。登場人物たちは一茶が犯人だとにらみ、一茶がいかに怪しい人物かということを証明するために劇中劇を演じる。
面白いのは、馬橋の大川立砂の姪、およねが登場するということ。およねは著者の創作であるらしい。
大川立砂の油屋に奉公している弥太郎(一茶)とおよねは、恋人で結婚の約束をしている。いずれ暖簾分けして、弥太郎は遊俳(俳句を趣味とする裕福な豪商など)になる予定だった。
ところが弥太郎はおよねを捨て、俳句を生業とする俳諧師(業俳)の道に入ってしまう。
この戯曲には、藤沢周平の小説に出てくる露光のような役回りで、立砂と弥太郎を引き合わせる竹里という俳諧師が登場する。
弥太郎と竹里は俳諧のライバルであり、およねを巡っては三角関係のようになり、竹里は弥太郎の行く先々で足を引っ張る。
富津の花嬌との恋文のやり取りがコミカルで笑いを誘う。
一方で、社会風刺の要素も込められている。

矢代静一『小林一茶』
矢代静一は昭和2年(1927)東京生まれの劇作家。「写楽考」「北斎漫画」などで知られる。平成10年(1998)に亡くなった。
『小林一茶』は『文藝』平成3年(1991)春季号に掲載された小説。
物語は一茶が亡くなった1年後に、助十という男が柏原を訪ねるところから始まる。
助十は馬橋の大川立砂のもとで弥太郎(一茶)と共に丁稚奉公していた。今は暖簾分けをしてもらい、江戸に油屋の店を開いている。助十は『一茶翁終焉記』と題された草稿を見せられて「生れつき清貧に甘んじ、俗人並の出世栄達に執着する気持は更になかった」「俳諧に於ける李白」という文章を見て「俺の知ってる弥太郎とはだいぶ違うぜ」と思う。この助十の気持ちはそのまま著者の気持ちだろう。
一茶の晩年を中心に印象的な場面がランダムに描かれる。
著者は一茶というよりは、その妻・菊に思いがあるらしい。菊が若くして亡くなったのは一茶が江戸で安い女を買って、悪い病気を菊にうつしたのではないかと疑っている節がある。
助十という人物は他の作品には出てこない。あるいは著者の創作かもしれない。
またこの作品には一茶の友人として葛飾北斎が度々出てくる。
劇作家らしく物語の途中に「幕間狂言」と題したエッセイが挟まれている。創作の過程などがわかる。
※参考文献=「まつど文学散歩」(宮田正宏・編)

一茶が大川立砂の墓参りに訪れた萬満寺
一茶と立砂、双樹
馬橋で油屋を営んでいた大川立砂は通称を平右衛門、また栢日庵とも号し、葛飾派の俳人であった。芭蕉、蕪村と並ぶ江戸時代の俳人・小林一茶は、立砂を爺(じじ)と呼んで親しみ、馬橋の立砂の許を足しげく訪れていたという。当時の一茶の経済状態は厳しく、立砂や流山の秋元双樹、布川の馬泉(ばせん)、守谷の西林寺住職鶴老などの同門俳人のところを訪れ、句会などを指導して、その謝礼で暮らしを立てていた。
安永6年(1777)、15歳の一茶は、故郷の信濃を出て江戸で生活を始めるが、「一茶」として頭角を現すまでの10年間は記録がない。そこで、地元では一茶は立砂のところで奉公していたという馬橋居住説が根強いが、確証がない。
一茶を題材に小説や戯曲を書いた作家たちは、豊かな想像力で、この空白の10年間を埋めている。
立砂が没し、一茶が信濃柏原に定住した後も、立砂の息子・斗囿との親交は続いたという。
流山で醸造業を営み、味醂の開発者の一人と言われる五代目秋元三左衛門(双樹)も一茶と親交があり、家業のかたわら俳句を習い、経済的にも支援していた。
流山は古くからコメの集散地で醸造業も盛ん。江戸川の水運にも恵まれたことから、江戸時代の後半から、みりんの町として栄えた。二代目堀切紋次郎の万上(まんじょう)みりんと秋元の天晴(あっぱれ)みりんが2大ブランドだった。
一茶双樹記念館には、秋元本家、一茶庵、双樹亭の3棟がある。秋元本家は幕末ごろの下総地方の商家建築を再現したもので、広い土間、畳敷きの店、格子戸、揚戸、箱階段などもしつらえてある。一茶庵は寄棟造り瓦葺きで再現。双樹亭は本格的書院造りで、安政年間(19世紀中頃)の建物を解体修理し復元したもの。同館の斜め向かいには「杜のアトリエ黎明」がある。
問い合わせは、☎04・7150・5750同館へ。
※参考文献=「松戸の歴史案内」(松下邦夫)