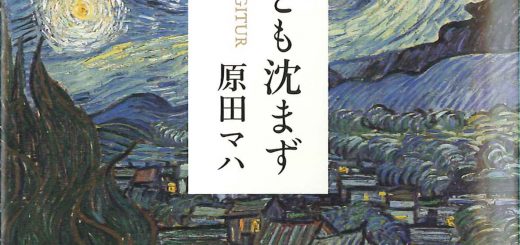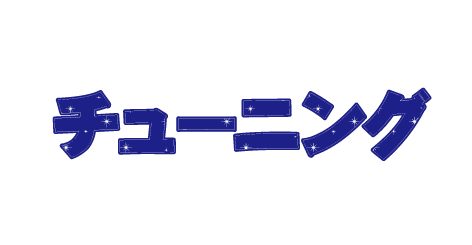本よみ松よみ堂
遠田潤子 著 『ドライブインまほろば』

 虐待された少年がたどり着いた峠のドライブインで見た光
虐待された少年がたどり着いた峠のドライブインで見た光
ドライブインまほろば
遠田 潤子 著
祥伝社 1700円(税別)
著者の作品を初めて読んだ。オビに「峠越えの〝酷道〟を照らす一軒の食堂。(中略)〝十年に一度の奇跡〟とは?」とある。
NHKの「ドキュメント72時間『ゆきゆきて 酷道439』」を思い出す。番組に出てくる〝酷道〟は、四国山地にある。狭い峠道で幅が2メートルしかなく、車が転落するのではないかとヒヤヒヤしながら見た覚えがある。
この作品に出てくる〝酷道〟は、奈良県にある。その峠道の途中にドライブイン「まほろば」があり、比奈子が一人で働いている。もともと「まほろば」は比奈子の祖父母が経営していて、比奈子も子どものころはよく遊びに来て、母と一緒に食堂の仕事を手伝っていた。祖父母のつくる料理は評判がよく、峠道でホッとできるドライブインは流行っていた。しかし、バイパスができてからは、峠を越える車もめっきり少なくなり、今では店を開けていてもほとんど客は来ない。一度は閉店した「まほろば」を無理に再開してもうまくいかないことは、比奈子にもわかっていた。5歳の幼い娘、里桜(りお)を亡くし、逃げるように「まほろば」に移り住んだのだ。里桜の名前は、ドライブインの入り口にある桜からつけた。里桜の死には比奈子の母が関係しているようだ。やり場のない怒りと悲しみ。やがて夫ともうまくいかなくなり、離婚した。
この作品の冒頭は、小学校6年生の少年・憂(ゆう)が義理の父親の流星という名の男を金属バットで殴り殺すというショッキングなシーンで始まる。事件を目の当たりにした憂の母親が気にしているのは死んだ流星のことばかり。読み始めてほんの数ページで、この母親の異常さと、憂の悲しみが伝わってくる。憂は流星のノートパソコンを奪い、5歳の幼い妹・来海(くるみ)を連れて逃亡の旅に出る。そしてたどり着いたのが、ドライブイン「まほろば」だった。
「生まれてきて……なんにもいいことなかった」。泣きながら、憂が比奈子にもらした言葉。
憂は実の父や義父の流星、実の母親に虐待さていた。だれにも愛されないことの悲しみ。唯一の家族は妹の来海だけ。だが、その大切な妹の実の父親を憂は殺してしまった。
流星には銀河という双子の兄がいて、憂の後を執拗に追跡してくる。憂が奪ったノートパソコンには、ある秘密が隠されていた。
比奈子は憂と来海をかわいがる。特に来海は亡くした里桜と同じ年頃の女の子。どうしても面影を重ねてしまい、苦しくなる。
憂の痛々しく悲惨な過去がだんだんわかってくるにつれ、読んでいても辛くなる。それだけに「まほろば」での穏やかなシーンにホッとする。この幸せなひと時がずっと続いてほしいと願わずにはいられない。
比奈子の憂と来海に対する気遣い、優しさ、いたわり。「そうだよなぁ。これが普通だよ」。読みながら何度もそう思う。
でも、それが普通だとは限らないんだよ、とこの作品は書いている(ように思える)。
憂の母親は「憂欝(ゆううつ)」の憂をとって名前をつけたという。子どもに無関心というより、むしろ憎んでいる。顔が嫌いな父親に似ているからだそうだ。この作品は名前の由来が一つのポイントになっている。
流星と銀河の兄弟も親に捨てられ、二人で生きてきた。とにかく、親の愛情を受けられなかった人たちが次々に登場する。
重く暗い話だが、不思議とページをめくる手が止まらない。それは、なんとか憂と来海に幸せな未来が待っていてほしい、生きてほしいと願うから。自分を犠牲にしても来海を守ろうとする憂のけなげさと、まだ無邪気な来海のかわいらしさに心を打たれるからだ。
二人の行方を執拗に追う銀河はまるで映画の「ターミネーター」みたいだ。最後までハラハラドキドキ。そして、最後に見える光に、涙があふれた。
【奥森 広治】