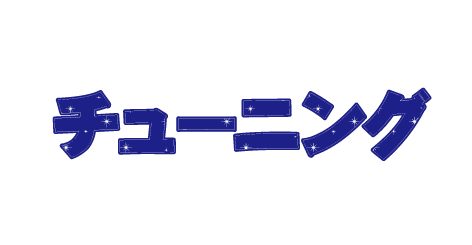本よみ松よみ堂
江戸を造った男
「世のため人のため」に大事業を成し遂げた男の生涯

 江戸を造った男
江戸を造った男
伊東潤著
朝日新聞出版 1800円(税別)
伊勢の貧しい農家に生まれた河村屋七兵衛(のちの瑞賢)は、荷車引き(車力)から身を起こして材木商となった。妻のお脇、3人の息子とつましい生活を送っていたが、明暦3年(1657)正月18日に起きた「明暦の大火」で息子を1人失ってしまう。失意の中、七兵衛が向かったのは木曽の山中。木材が高騰する前に山林を買い占め大金を得た。しかし、七兵衛が材木を買い占めたのは、欲のためではなかった。七兵衛は木材で得た金を米にかえ、寒い冬に大火で焼け出された人々のために粥施行(かゆせぎょう)を行った。しかし、被災者はあまりにも多く、買い付けた米はすぐに底をついてしまう。困っていたところ、七兵衛の噂を耳にした大阪の商人たちが援助を申し出てくれた。
やがて問題になったのが、江戸の町や江戸湾に残された多くの遺骸。幕府は遺骸の処理にまでは手がまわらず、気温が上がれば疫病が蔓延する危険が出てきた。七兵衛は一計を案じ、芝の増上寺を訪れていた将軍後見役の保科正之に命懸けで直訴。このことがきっかけで、保科正之とのつながりができ、七兵衛は東回り・西回りの海運航路の整備、越後高田藩の治水事業と銀山開発、大阪・淀川の治水工事など、大きな事業を任されるようになる。
七兵衛は次々に大きな仕事を成し遂げていくが、仕事を引き受けるかどうかの基準になるのが「世のため人のためになるか」ということ。例えば、東回り・西回りの海運航路の整備は、人口増加が進む江戸の庶民を飢えさせないためには、どうしても東北地方の米を安全に江戸まで送る仕組みが必要だったからだ。そのポリシーは、最初に挙げた明暦の大火のエピソードに集約されている。七兵衛は利益を上げるために材木を買い占めたのではなく、それを全て米に変えて被災者に施した。そのことが河村屋の名前を知らしめ、やがて大阪商人たちの善意を促した。多くの人の利を考えたことが、やがて自分にめぐってくる。この経験で七兵衛が得た最大のものは「心の充足感」といったものではなかっただろうか。また、遺骸の処理を命懸けで幕府に訴えたのは、もちろん疫病の懸念もあるが、助けられなかった息子への思い、あの遺骸の山の中には、きっと息子もいるといった思いもあるだろう。
七兵衛の人心掌握術にも学ぶべきところが多い。幕府の直轄事業なのだから、その権威を使って有無を言わさず仕事を推し進めることはできる。しかし、七兵衛は権威を笠に着ることなく、相手の身分に関係なく低姿勢で臨み、信頼できる協力者を見つけていく。どんな大事業も、成否の鍵は結局人間である。
七兵衛は地方にまで名が知られた豪商となっていくのだが、その心根から、読んでいると清(すが)しい気持ちになる。
【奥森 広治】